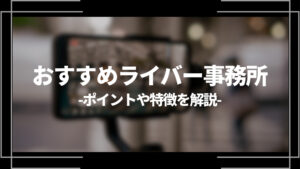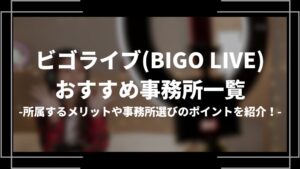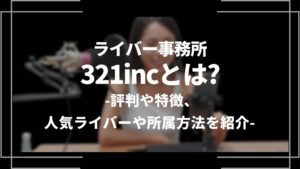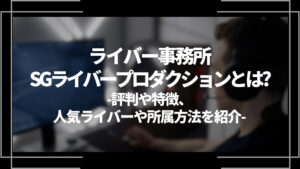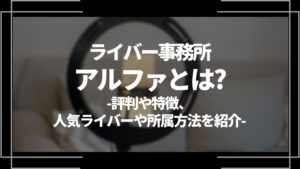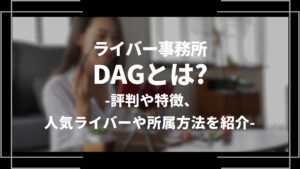「声を使った仕事にはなにがある?」「在宅でできる声を使った仕事はあるの?」
上記のような疑問をお持ちではないでしょうか。
声を使う仕事にはさまざまあり、知名度が高いものだけでなく、あまり知られていない仕事もあります。
本記事では声を使う仕事を8選紹介しつつ、未経験や在宅でできる仕事も解説します。
声を使う仕事に就きたい人や声に自信がある人は、本記事を参考にして自分に合う仕事を見つけてみてください。
また、声を使う仕事の中でも特におすすめなのは「ライバー」です。
これからライバーとして声を使って仕事をしたい人は、下記の安全性・信頼性が高いライバー事務所への所属がおすすめです。
| ライバー事務所 | 特徴 | 公式サイト |
|---|---|---|
 Nextwave |
| 公式サイト |
 321inc |
| 公式サイト |
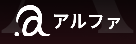 アルファ |
| 公式サイト |
なお、おすすめのライバー事務所のランキングを以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
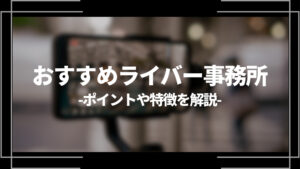
声を使う仕事8選

声を使う仕事には、主に以下8つが挙げられます。
- ライバー・Vtuber
- 声優
- ナレーター
- アナウンサー
- 司会・MC
- ラジオパーソナリティ
- 歌手・アーティスト
- ボイストレーナー
以下で1つずつ解説するため、自分に合っている仕事を見つけてみてください。
ライバー・Vtuber
声を使う1つ目の仕事は、ライバー・Vtuberです。
ライバーやVtuberはライブ配信をしながら、リスナーとコニュニケーションをとるのが主な仕事内容となっています。
特別なスキルや資格は必要なく、スマートフォン一台で仕事ができるため、在宅でもできる仕事として人気があります。
また、ライブ配信は顔出しをする方が稼ぎやすいものの、近年はイラストで配信できるVtuberも人気です。
家族や知人にバレたくない人や、身バレが怖い人も安心して挑戦できます。
人とコミュニケーションをとることが好きな人や、在宅で声を使う仕事がしたい人にライバーやVtuberはおすすめです。
声優
声を使う2つ目の仕事は、声優です。
声優は、アニメや映画などに登場するキャラクターの声を担当する仕事です。
キャラクターごとの性格や感情を声で表現する必要があるため、高い解釈力が求められます。
また、ひとつのキャラクターだけでなく、さまざまな役に対応できる柔軟性も必要です。
性格や感情を声に表すのが得意な人や、俳優や女優のように顔を出すのは抵抗があるけど声に自信がある人に声優はおすすめといえます。
ナレーター
声を使う3つ目の仕事は、ナレーターです。
ナレーターとは、一言でいうと「語り」を指しており、テレビ番組やラジオ番組でナレーションを行う仕事です。
たとえば、バラエティ番組などを見ていると、状況を声だけでわかりやすく解説する人を見受けます。
映像をわかりやすく視聴者に伝えることはもちろん、シーンに合わせて面白さや楽しさを声で演出するスキルが求められます。
朗読が好きな人や表現力が豊かな人は、ナレーターに挑戦してみてはいかがでしょうか。
アナウンサー
声を使う4つ目の仕事は、アナウンサーです。
アナウンサーは広く知られている声を使う仕事で、ニュース番組で情報を伝えたり、バラエティ番組の司会を務めたりなど内容はさまざまです。
アナウンサーは非常に人気がある仕事なため、難易度は非常に高めな傾向にあります。
また、ニュース番組では速報が入るなど、予定した放送内容が変更される場合があり、柔軟に対応できる能力も求められます。
正しい発音や的確なインタビュー内容など、スキルはやや必要になりますが、自分の意思をしっかり伝えられる人や愛嬌がある人にはおすすめです。
司会・MC
声を使う5つ目の仕事は、司会・MCです。
司会・MCはテレビ番組や音楽番組などで進行を務める人を指しており、場を仕切る能力やコミュニケーション能力が求められます。
また、バラエティ番組では視聴者を盛り上げたり、笑いを誘ったりするために、エンターテイメント性も必要です。
ほかにも、生放送でトラブルが起きた場合は、冷静に対処して流れを崩さないことも司会MCとしての重要な役割です。
おしゃべり好きな人や出演者・ゲストそれぞれに配慮をしながら司会進行できる人に、司会・MCは向いています。
ラジオパーソナリティ
声を使う6つ目の仕事は、ラジオパーソナリティです。
ラジオパーソナリティとは、ラジオ番組の司会や進行を務める仕事です。
テレビ番組などとは異なり、声だけで番組の進行を行うため、顔を出すのに抵抗がある人におすすめできます。
ただし、顔を出さない分声で感情を伝えたり、状況を伝えたりといったスキルが求められます。
自分が伝えたいことを伝えられたり、自分の進行でリスナーを楽しませたりできる点は、ラジオパーソナリティとしてのやりがいといえるでしょう。
歌手・アーティスト
声を使う7つ目の仕事は、歌手・アーティストです。
歌手・アーティストは幅広く存在しており、アイドルグループやバンド、K-POP、シンガーソングライターなどさまざまです。
特別な資格なども必要がなく、ずば抜けた歌唱力を持っていれば、歌手・アーティストを目指せる可能性があります。
歌うことが好きな人や自分の思いを歌詞で表現したい人に、歌手・アーティストはおすすめといえます。
ボイストレーナー
声を使う8つ目の仕事は、ボイストレーナーです。
ボイストレーナーは、歌手や俳優など声を使う人に対して、発声練習や声の使い方を指導する人を指します。
豊富な経験や実績、指導力などが求められるため、未経験では難しい仕事といえます。
また、それぞれテクニックや声の使い方が異なるため、一人ひとりのニーズに合わせて指導することが大切です。
ボイストレーナーになりたい場合は、音楽系やボイストレーナー関係の専門学校で基礎やスキルについて学ぶことをおすすめします。
在宅で稼ぎたい人はライバーがおすすめ
声を使う仕事にはさまざまな仕事がありますが、在宅で稼ぎたい人はライバーがおすすめです。
特別な資格やスキルは必要がなく、スマートフォン一台で仕事ができるため、場所や時間を問わず自由に働ける点が魅力といえます。
なお、ライバーで稼ぎたい人はライバー事務所に所属することで、ノウハウの提供やサポートを受けることができます。
おすすめのライバー事務所を以下の表にまとめたので、気になる人はぜひ相談してみてください。
| ライバー事務所 | 特徴 | 公式サイト |
|---|---|---|
 Nextwave |
| 公式サイト |
 321inc |
| 公式サイト |
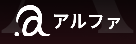 アルファ |
| 公式サイト |
声を使う仕事に関するよくある質問【Q&A】

声を使う仕事に関するよくある質問をまとめました。
- 声を使う仕事は未経験でもできる?
- 在宅でできる声を使う仕事はある?
- 声を使う仕事は副業にできる?
- 声を使う仕事は資格なしでもOK?
- 声を使う仕事で気をつけるべき喉のケア方法は?
それぞれ回答してきます。
声を使う仕事は未経験でもできる?
声を使う仕事の中には、未経験でもできる仕事もあります。
もちろん、中には専門学校など知識や経験が求められるものもありますが、独自の感性で始められる仕事もたくさんあります。
たとえば、ライバーなら特別な資格やスキルは必要がなく、未経験でも可能です。
在宅でできる声を使う仕事はある?
在宅でできる声を使う仕事には、ライバーやVtuberが挙げられます。
ライバーやVtuberはスマホやパソコンがあれば配信を行えるため、自宅などの好きな場所で働くことができます。
そのため、子育てや家事の合間に仕事がしたい主婦の人や、家で仕事がしたい社会人にもぴったりです。
声を使う仕事は副業にできる?
本業とは別に副業として声を使う仕事をすることも可能です。
日中は本業をして、帰宅後や休日などの時間を有効活用することができればお金を稼げることはもちろん、日々の暮らしを充実させられます。
そのため、声を使う仕事に興味がある人は、副業として始めてみるのもひとつの方法です。
しかし、副業が禁止されている会社に属している場合は、副業ができないため注意してください。
声を使う仕事は資格なしでもOK?
声を使う仕事の多くが、特別な資格は必要としていません。
仕事によっては経験やコネクションが求められるものもありますが、必ずしも資格が必要なわけではないため未経験でもやる気次第で挑戦できます。
とくにライバーやVtuberは資格や経験なしですぐに始められるため、声を使う仕事に挑戦したい人におすすめです。
声を使う仕事で気をつけるべき喉のケア方法は?
喉のケア方法としてうがいをしたりのど飴等を舐めたりする以外に、常に乾燥を避け一定の湿度を保つこともひとつです。
また、喉を酷使すると声質や声量に影響が出るため、声帯を傷つけない発声方法を身につけることもケア方法といえます。
声を使う仕事における主役は「声」であり、喉のケアは必要不可欠です。
ケア方法や予防策を実施して、常に魅力的な声を届けましょう。
【まとめ】声を使う仕事は豊富!未経験でも積極的にチャレンジしてみよう

声を使う仕事は豊富にあり、ライバーや声優、ナレーターなどさまざまです。
もちろん経験がある方が優遇されやすいですが、ほとんどは未経験からでも可能なため、積極的にチャレンジしてみてください。
また、在宅で声を使う仕事がしたい人は、ライバーがおすすめです。
ライバーならスマートフォン一台でOKなため、自宅で好きな時間に仕事ができます。
本記事を参考にして、自分に合う声を使う仕事を見つけてみてください。
なお、おすすめのライバー事務所のランキングを以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。